こんにちは!池田塗装の池田です。
今日は、「サイディングの気になる隙間、埋めるべきか?」についてお伝えします。
外壁のサイディングにできた小さな隙間を見つけると、「このままで大丈夫なのかな?」「雨漏りの原因にならない?」と不安に思う方は多いです。実際、お客様からも「この隙間って埋めた方がいいですか?」というご相談をよくいただきます。
結論から言うと、サイディングの隙間には「埋めるべき隙間」と「埋めてはいけない隙間」の2種類があります。すべてをコーキングで塞いでしまうと、通気が妨げられ、かえって劣化を早めるケースもあります。逆に、埋めずに放置すると雨水が侵入し、ボードの反りや浮きの原因になることもあります。
つまり、サイディングの隙間は「見た目が気になるから」といって埋めるのではなく、その隙間がどんな役割を持っているのかを見極めることが重要なのです。
この記事では、
- 埋める必要がない隙間とその理由
- 補修が必要な隙間の見分け方
- 絶対に埋めてはいけない隙間と注意点
を、プロの目線でわかりやすく解説していきます。
目次
サイディングの隙間は「埋めるべき」と「埋めてはいけない」がある?

外壁のサイディングに見える小さな隙間。ぱっと見では「ここから雨水が入るのでは?」と心配になりますよね。ですが、実はこの隙間には大きく分けて「埋めるべき隙間」と「埋めてはいけない隙間」の2種類があるのです。
「隙間=悪いもの」と思い込みがちですが、サイディングにはもともと「呼吸する外壁」としての構造があり、通気や水切りのためにあえて隙間を設けている部分も存在します。ここをむやみに埋めてしまうと、湿気がこもり、ボードの劣化を早めてしまうこともあります。
逆に、劣化や経年変化でできた「埋めるべき隙間」を放置すると、雨水の侵入やカビ、さらには外壁内部の腐食を引き起こす可能性があります。ですから、どの隙間を補修すべきで、どの隙間は触らない方がいいのかを見極めることが、長持ちする外壁を保つための第一歩になります。
まず理解すべき「サイディングの構造」
サイディングは「外壁の板材(ボード)」を建物の外側に貼り合わせて作る仕上げ材です。特に一般的な窯業系サイディングボードは、セメントを主成分とした板を建物に張り付け、その継ぎ目をコーキング(シーリング)材でつないで防水しています。
横方向のボード同士は「相じゃくり」と呼ばれる“重ね合わせ構造”になっており、水が入りにくいように加工されています。つまり、ボードが少し重なり合うことで、水が中に入りにくく、外へ流れ出るよう設計されているのです。
この構造を理解しておくと、「隙間がある=施工不良」とは限らないことがわかります。むしろ空気の通り道や水の逃げ道として、外壁全体の通気を確保している場合もあります。
よくある誤解「隙間がある=施工不良では?」
お客様から「外壁の板の間に隙間が見えるのは施工ミスですか?」と聞かれることがあります。ですが、多くの場合、これは正常な状態です。
例えば、サイディングの横方向のつなぎ目には、塗装後でもわずかな隙間が見えることがあります。これは、ボードを重ねた際にできる“呼吸のためのすき間”であり、構造上の必要部分です。
ここを「見た目が気になる」といってコーキングで完全に埋めてしまうと、通気が妨げられ、内部に湿気がこもる原因になります。結果として、サイディングが反ったり、塗膜が早く劣化したりすることもあります。
一方で、コーキング材が切れてしまっている「縦の目地」や「窓まわりの隙間」は別問題。ここは防水上の要ですので、放置すると雨水が建物内部に侵入します。見た目は小さな隙間でも、補修を怠ると下地まで腐食してしまう恐れがあるのです。
つまり、「隙間がある=悪い」とは限らず、場所と構造によって“必要な隙間”か“危険な隙間”かが異なるということを理解しておくことが大切です。
埋める必要がない隙間(横の継ぎ目など)

外壁サイディングの隙間には、実は「埋めない方がいい」部分があります。
その代表が、横方向の継ぎ目(ジョイント部分)です。
ここは見た目上「隙間がある」と感じるかもしれませんが、構造上の理由からあえて隙間を残す設計になっています。
横の継ぎ目はなぜ埋めないのか
サイディングボードは、横に長く張り合わせて施工する「横張り」が一般的です。
このとき、ボードの継ぎ目部分には「相じゃくり(あいじゃくり)」と呼ばれる加工が施されています。これは、ボード同士を少し重ね合わせて、雨水が中に入りにくく外に流れ出やすくするための構造です。
つまり、見えている隙間は「水を逃がすための排出口」のようなもので、ここをコーキングで埋めてしまうと、かえって内部に水分がこもり、湿気による劣化を早めてしまうおそれがあります。
この横の隙間は、“呼吸する外壁”のために必要な通気部分です。埋める必要はなく、むしろ通気や水切りの機能を損なわないように保つことが大切です。
塗装時の注意点
外壁塗装を行う際、この横の継ぎ目部分には注意が必要です。塗装時に塗料が入り込むと、隙間が部分的に埋まって「塗料が入った箇所」と「入らなかった箇所」でまだらになることがあります。
見た目としてはムラのように感じられるかもしれませんが、構造的にはまったく問題ありません。それでも「正面だけでもきれいに仕上げたい」というお客様の希望がある場合は、人目につきやすい部分だけに専用の充填材を使って軽く埋める方法もあります。
ただし、この場合でも外壁全体を埋めてしまうのは厳禁です。通気が妨げられると内部結露や膨張・収縮による塗膜剥がれを引き起こす可能性があります。見た目の美しさを重視するあまり、外壁の性能を損なわないよう注意が必要です。
埋めないことで得られるメリット
横の継ぎ目を埋めずに残しておくことで、以下のようなメリットがあります。
外壁内の湿気が自然に逃げるため、内部結露を防げる
ボードの膨張・収縮による塗膜割れを抑えられる
雨水の排水経路が確保され、外壁の耐久性が上がる
サイディングは「通気性」と「防水性」を両立させるために緻密に設計されています。このバランスを崩さないためにも、構造上の隙間はそのまま残しておくことが理想的です。
補修が必要な隙間(埋めるべきケース)

外壁のサイディングにできる隙間の中には、放置してはいけない危険な隙間もあります。
それが「防水の役割を果たす部分」や「ボード自体の劣化によって生じる隙間」です。これらをそのままにしておくと、外壁内部に雨水が侵入し、カビ・腐食・膨張などの原因となります。
ここでは、補修が必要な代表的な3つのケースについて詳しく見ていきましょう。
縦目地(コーキング部)の劣化
サイディングボードの「縦の継ぎ目」は、防水と緩衝のためにコーキング(シーリング)材が充填されています。このコーキングは、雨水の侵入を防ぎ、さらに地震や温度変化による外壁の動きを吸収する重要な役割を担っています。
しかし、経年劣化によってこのコーキングが次第に硬くなり、ひび割れ・切れ・剥がれなどが起こります。こうなると、雨水が内部に侵入し、外壁の下地や断熱材が湿ってカビが生えたり、内部の木材が腐ってしまう危険があります。
補修方法としては、基本的に「打ち替え工法」が行われます。これは古いコーキングをすべて撤去し、新しい材料を充填する方法です。上から重ねるだけの「打ち増し」よりも確実で、防水性能をしっかり回復できます。
この作業を怠ると、見えない部分でダメージが進行してしまうため、10年に一度を目安に点検・補修を行うことが大切です。
窓(サッシ)まわりの隙間
次に注意が必要なのが、窓の縁(サッシまわり)のコーキング部分です。サッシと外壁の取り合い部分は、雨が直接当たる場所でもあるため、非常に劣化しやすいポイントです。
ここに隙間ができると、雨水が内部へと侵入しやすくなり、「室内の壁紙が浮いてきた」「サッシの下側が黒ずんでいる」などの症状が現れることもあります。
このような隙間は早期補修が必須です。補修の際には、古いコーキングを完全に取り除き、プライマー(下塗り材)を塗布してから新しいコーキング材を充填します。しっかりと乾燥させることで、長期間にわたり防水性を保つことができます。
サッシまわりの補修は一見簡単そうに見えますが、DIYでやると密着不良や逆流トラブルを招くことが多いため、専門業者に任せるのが安心です。
サイディングの「反り」や「浮き」による隙間
サイディングボード自体の反り・浮きによってできる隙間も、早急に対処が必要です。この現象は、経年劣化や日射・湿気による膨張と収縮の繰り返しで起こります。
最初は小さな隙間でも、そこから雨水が侵入し、ボードの断面(塗装されていない切り口)が水を吸うことで内部が膨張。乾くと再び縮むというサイクルを繰り返すうちに、ボードの変形が進み、やがて反り・浮き・割れといったトラブルを引き起こします。
このような場合、ただコーキングで隙間を埋めるだけでは根本解決になりません。ボードの固定ビスを打ち直す、もしくは張り替えを行う必要があります。また、塗装の前に下地をしっかり補修しておかないと、いくら上からきれいに塗っても長持ちしません。
こうした反りや浮きは、専門業者でなければ判断が難しいため、早めに点検を依頼することが重要です。
補修が必要な隙間を放置するとどうなる?
補修を怠ると、次のような症状が現れます。
- 雨漏りや内部結露の発生
- ボードの膨張・ひび割れ
- 下地材や断熱材の腐食
- カビ・シロアリ被害の発生
これらは、見た目の問題だけでなく、建物全体の寿命を縮める重大なリスクです。
サイディングは「塗る前の下地補修」で寿命が決まるといっても過言ではありません。
外壁を長く守るためには、早めの点検と適切な補修を行うことが何より大切です。
絶対に埋めてはいけない隙間

ここまで「埋めるべき隙間」と「埋めなくていい隙間」を解説してきましたが、もう一つ知っておいてほしいのが、“絶対に埋めてはいけない隙間”です。この隙間を塞いでしまうと、外壁内部の湿気や雨水が逃げ場を失い、結果的に内部腐食や雨漏りを悪化させてしまいます。
とくにDIYでの補修や、他業種による簡易補修で誤って塞がれているケースが非常に多く見られます。
水切り(基礎上)の下の隙間
外壁の一番下、基礎の上に取り付けられている「水切り板金」の下にある隙間。この部分には、見た目上「外壁と基礎の間にすき間がある」と感じられることがあります。しかし、ここは建物の内部で発生した湿気を逃がすための通気口のような役割を持っています。
水切りの下の隙間をコーキングで塞いでしまうと、内部の湿気がこもり、外壁材や木材の腐食・カビ・結露の原因になります。また、内部に入った雨水の逃げ場がなくなり、外壁の裏側に水が溜まってしまうこともあります。
実際に現場でも「雨漏りを止めようとして水切りを塞いだ結果、逆に被害が拡大した」というケースをよく見かけます。水切り下の隙間は埋めてはいけない代表例です。
ベランダ笠木(かさぎ)の下の隙間
次に注意すべきなのが、ベランダの手すり上部にある「笠木(かさぎ)」の下の隙間です。ここも一見すると雨水が入りそうに見えますが、実は水の出口(排水経路)として設計されています。
雨水がベランダ内側や外壁内部に入った際、この隙間を通じて排出される仕組みになっているため、ここを塞ぐと水が内部に溜まり、笠木下の木材や防水シートが腐る原因となります。
とくにアルミ製やガルバリウム製の笠木は内部が見えにくいため、「見た目をきれいにしよう」とコーキングを打ってしまうと、気づかないうちに内部腐食が進行していることがあります。
笠木まわりの防水は非常にデリケートな部分です。少しの判断ミスで、雨漏りや躯体劣化を招く可能性があるため、専門業者による点検と補修が不可欠です。
通気口や換気スリットまわりの隙間
サイディングの中には、壁体内の通気を促すために設けられ換気スリット(通気口)が存在します。
この部分も、外から見ると「穴が開いている」「隙間がある」と感じやすい箇所ですが、
ここを塞いでしまうと、内部の湿気や熱気が排出されず、結露・カビ・断熱性能の低下を引き起こします。
換気口まわりにホコリや虫が入るのを気にして、DIYで塞ぐ方もいますが、通気経路を遮断してしまうと、外壁の劣化が一気に進行します。必要な通気部分はそのままの状態を保つことが鉄則です。
DIY補修でやりがちな失敗例
以下のような行為は、現場でよく見かける「やってはいけない補修」です。
- 水切りや笠木下をコーキングで完全に塞ぐ
- 通気口を防虫ネットやパテで塞ぐ
- 隙間を全部埋めれば“防水できる”と勘違いする
こうした対処は一時的に安心感を得られるものの、長期的にはトラブルの原因になります。
「隙間をなくすこと=防水」ではなく、適切に水を逃がす構造を維持することが本当の防水です。
まとめ~横浜市での外壁塗装・屋根塗装なら
本記事では、サイディングの隙間について「埋めるべき隙間」と「埋めてはいけない隙間」の違いを詳しく解説しました。一見するとどれも同じように見える外壁の隙間ですが、その役割は場所によって大きく異なります。
横の継ぎ目(相じゃくり部)のように通気や水切りのために設けられた隙間は、埋めてしまうと外壁が呼吸できなくなり、内部の湿気がこもって劣化を早めます。一方、縦の目地やサッシまわりなどコーキングが劣化してできた隙間は、雨水の侵入経路になるため早急な補修が必要です。また、水切り下やベランダ笠木下といった排水経路を塞ぐと、内部腐食や雨漏りを悪化させてしまうこともあります。
つまり、「隙間=悪いもの」と決めつけるのではなく、その隙間が“何のために存在しているのか”を正しく見極めることが何より重要です。
もしご自宅の外壁に隙間を見つけたときは、焦ってDIYで塞いだりせず、専門業者に点検を依頼することをおすすめします。正しい判断と適切な補修を行うことで、外壁の寿命を大きく延ばすことができます。
池田塗装は、横浜市を中心に20年以上地域密着で施工を行う大規模修繕・外壁塗装の専門店です。これまでに4,000件を超える施工実績があり、戸建て住宅からマンション、商業施設まで幅広く対応してきました。
当社では、すべてのお客様の建物を経験と技術を持った自社の専門職人が責任を持って施工しています。「お客様に対して誠実であること」を何より大切にし、仕上がりの美しさはもちろん、施工後の安心まで見据えた対応を徹底しています。
外壁の隙間やサイディングの劣化が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。現場を熟知した診断士が、建物の状態を丁寧に点検し、「埋めるべきか・埋めないべきか」を正確に見極めてご説明いたします。
横浜市で外壁の補修や塗装をお考えの方は、地元密着の池田塗装に安心してお任せください。
「こんな相談しても嫌がられないかな?」
「まだやるか決めていないんだけれど…」
など、ご心配不要です。
「HPを見たのですが…」と、0120-711-056(年中無休7時〜19時)まで、お気軽にお電話下さい。
「HPを見たのですが…」と、0120-711-056(年中無休8時〜19時)まで、お気軽にお電話下さい。
川崎市・横浜市を中心に神奈川県全域が施工エリアになります。お家の外壁塗装、屋根塗装は職人直営専門店の「池田塗装」にお任せください。
- 【川崎本店】TEL:0120-711-056
- 【川崎南店】TEL:0120-711-056
- 【横浜青葉店】TEL:0120-824-852
川崎本店:〒216-0042 神奈川県川崎市宮前区南野川2-35-2
アクセスはコチラ
川崎南店:〒210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎4-18-22
アクセスはコチラ
横浜青葉店:〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1603-2
アクセスはコチラ
【公式】YouTubeはコチラ
【公式】Instagramはコチラ
この記事の著者について

-
2021年3月31日、はじめて執筆の書籍「リフォームで一番大切な外壁塗装で失敗しない方法」をクロスメディア・パブリッシングより出版。(各図書館に置かれています)
「初心忘るべからず」という言葉を胸に、毎日お客さまの信頼を得られるよう頑張っています。 世の中には不誠実な業者も多く、リフォームで後悔する人が後を絶ちません。
一人でもそういう方がいなくなり、私たちが地元の皆さまに貢献できればと思っています。川崎市・横浜市にお住まいで、外壁塗装についてお悩みの方はお気軽にご相談下さい。(会社概要・本店について|青葉店はこちら)


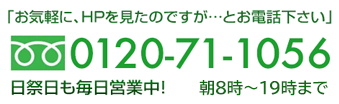



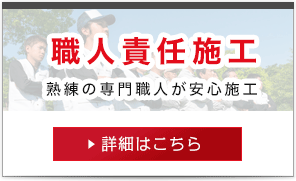
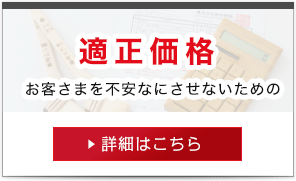

















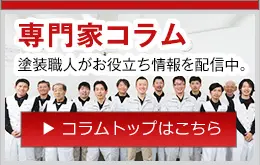
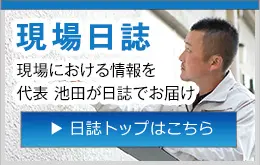

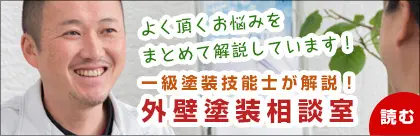



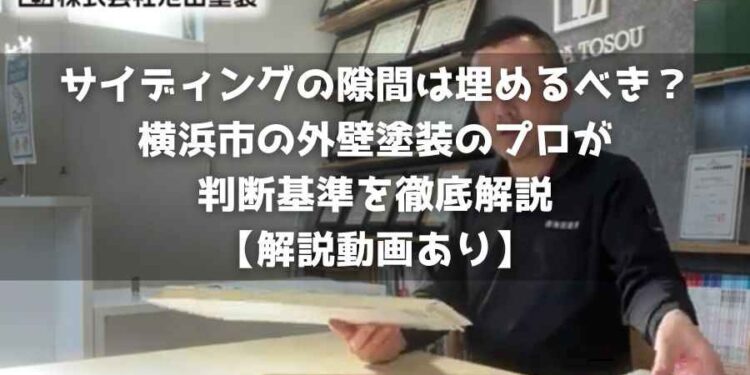
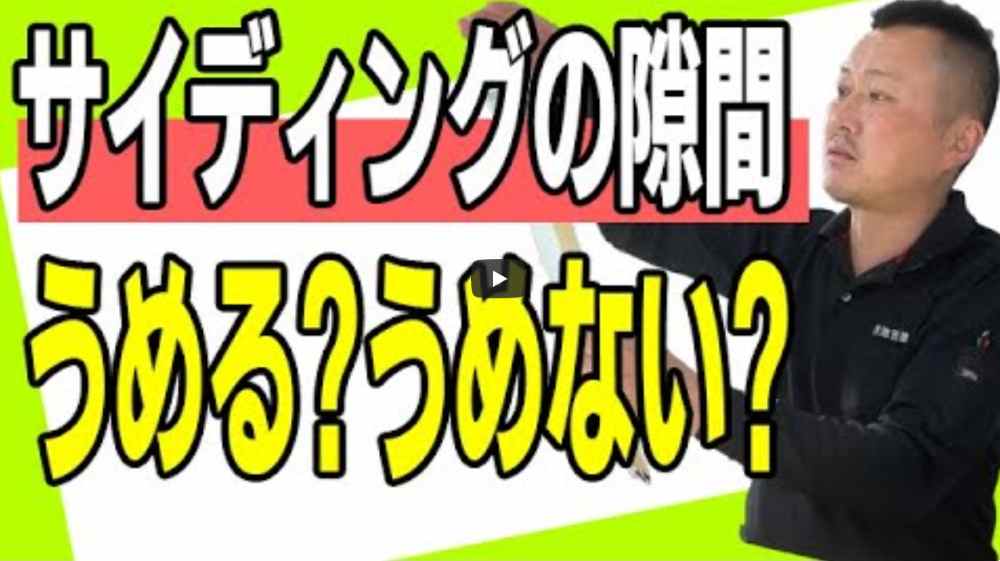
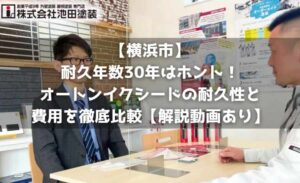
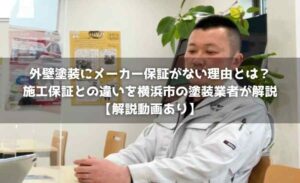
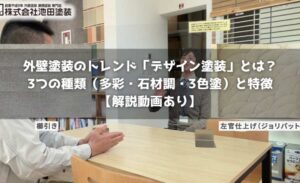
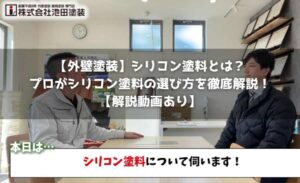
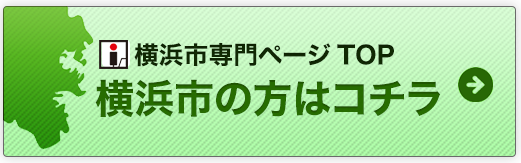
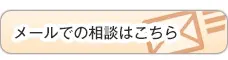

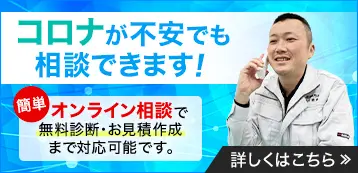

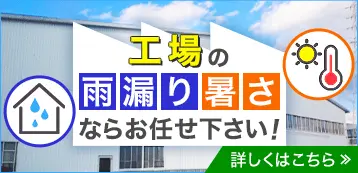
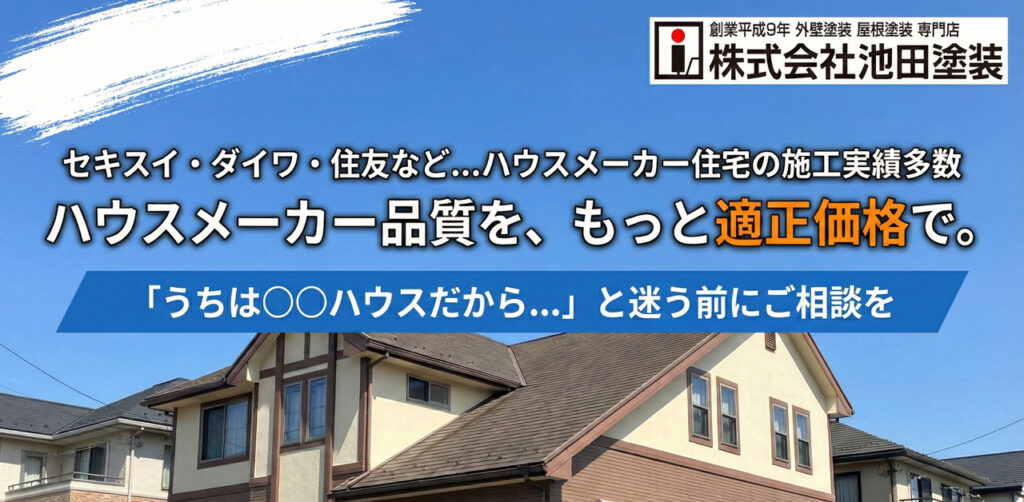













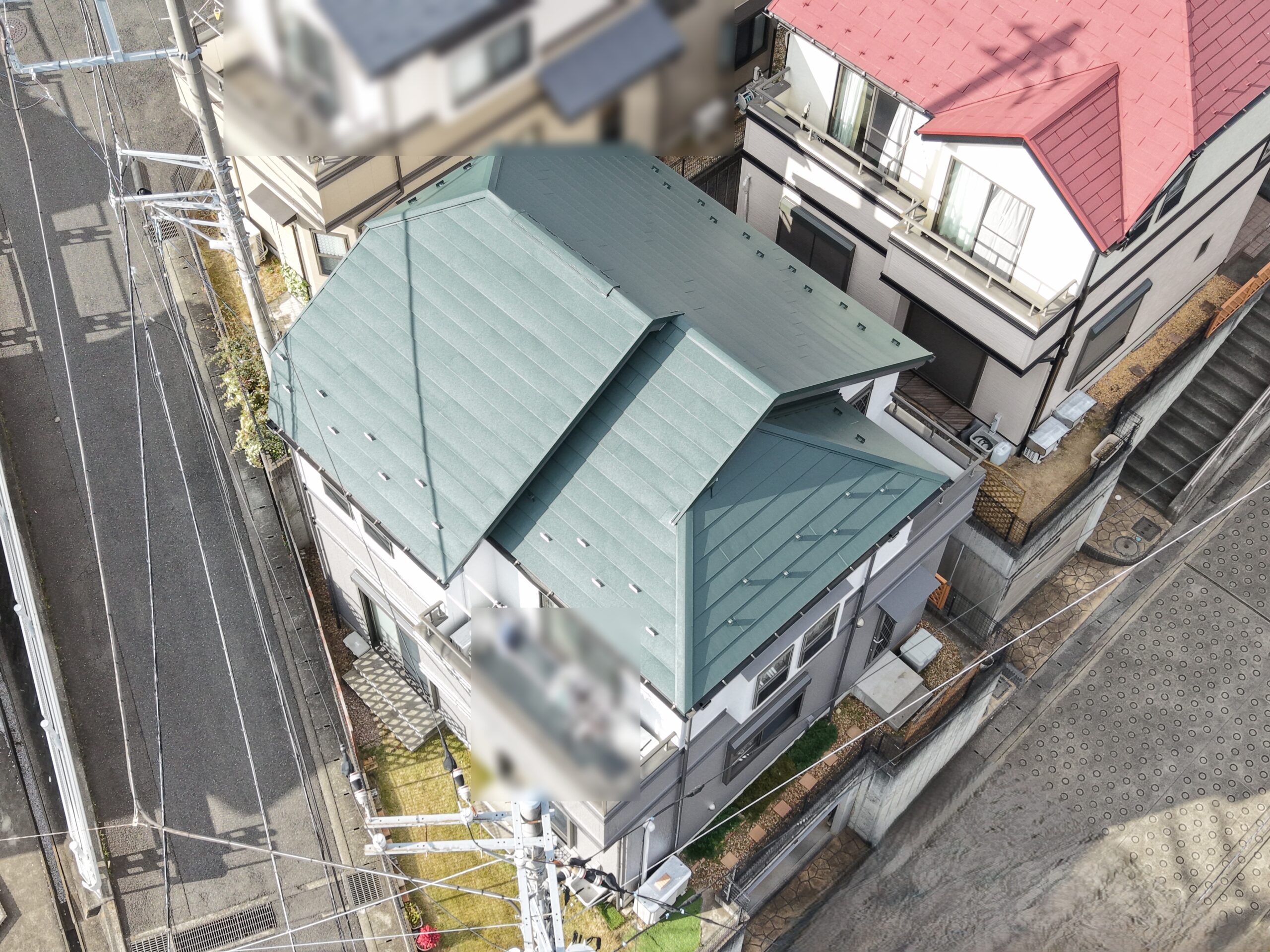

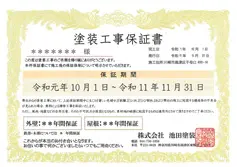
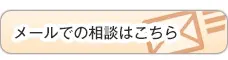


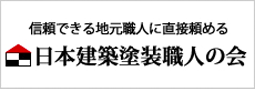


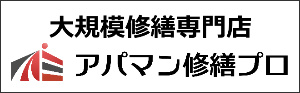
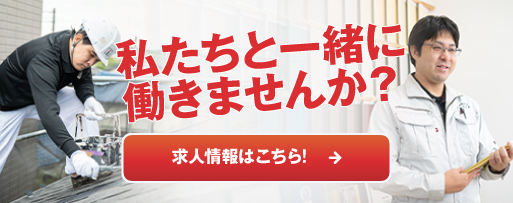
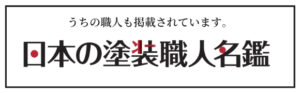

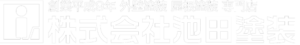
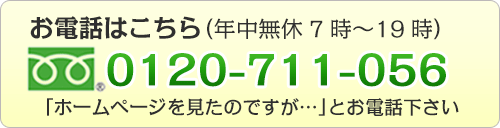

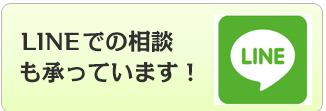
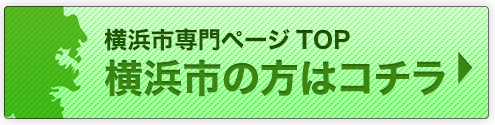
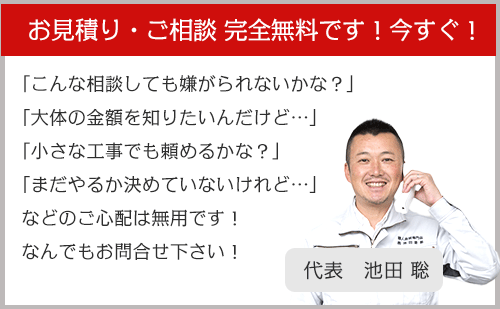
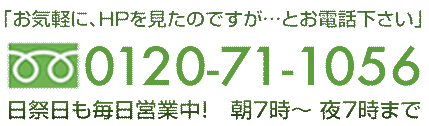


 お問い合せ
お問い合せ